気温が上昇をはじめる時期に、ひときわ人々の目を輝かせる現象が起きます。それは野山や公園に咲く桜の花。
非常に美しいです。
花見は、四季のある日本で自然の移り変わりを身近に感じることができる嬉しい伝統ですね。
そして、季節の変化を敏感に感じた桜の木が蕾をつくり、やがて花を咲かせますが、実は桜にはある条件があります。この条件を知ることで桜の開花を予想することが可能です。
では、どの条件で桜は花を咲かせるのでしょうか?
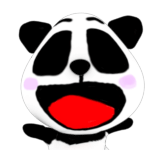
今年も桜がさきそうパラ、桜の開花宣言の条件はなにパラ?
桜の開花が宣言される条件とは?

四季のある日本において、自然の移り変わりを肌で感じることができます。特に、冬開けの春では桜が咲き誇り、花見などをして大きな季節の変化を感じられます。
「毎年行われる ” 開花宣言 ” 」
一度はテレビや現地で見た人も多いのではないでしょうか?
職員が桜を見ながら開花をしたことを確認すると、そこではじめて今年の桜が咲いたことになります。
桜の開花予想は1950年頃から気象庁により発表されています。テレビなどで見る職員風の人は気象庁の人です。開花宣言と予想が発表されるのですが、双方の発表時期は当然ながら違います。
桜開花予想は毎年1月頃に1回目が発表されています。何を基準にして発表しているのかというと、桜の赤ちゃん。つまり「花芽」を元にして予測をしています。
花芽がつぼみに変化すると、桜の花が咲くカウントダウンがはじまります。
観測用のソメイヨシノ
桜の木は品種改良によりさまざまな種類が存在するため、気象庁は観測用の桜を選んでいますが…。
「その桜の対象は ” ソメイヨシノ “ 」
気象庁も予想をたてるのですが、実は個人でも桜の開花予想をたてることが可能です。
冬から春までの1か月・3か月の気温予想を調べ、気温推移の予測が当たれば、開花予想日も数日程度の誤差で的中させることができます。
ちなみに、開花宣言の条件は全国各地にある標本木の花の状態で決めることができますが、気象庁では蕾が5、6綸ほころんだ状態になったときに桜の開花宣言を出しています。
つまり、対象の標本木には桜がまったく咲いていない。でも、横にある木には桜が10綸以上も咲いている場合は、「桜はまだ開花していない」となります。
桜の開花宣言ができるのはあくまでも対象にしている標本木に限られます。
また、開花の先にあるのは桜の「満開」です。満開だと判断をしているのは、標本木の80%以上のつぼみが開くことを条件にしています。これは機械などは使わずに人による目視で判断します。
対象木
- 木の種類 …染井吉野(ソメイヨシノ)
- 木の場所 …全国の標本木を対象に観測
開花から満開の日数と桜が咲く400℃・600℃の法則

- 北海道地方 …約4日
- 北陸・東北地方 …約5日
- 九州から東海・関東地方 …約7日
- 沖縄・奄美地方 …約16日
※目安
桜が咲く頃がわかる法則であります。
その方法とは、2月以降の毎日の平均気温を足していき、その合計が400℃前後・600℃前後に到達すると桜が開花を迎えるというもの。
誰が見つけたのかはわかりませんが面白い法則ですね。
お湯は100度をこえると沸騰します。桜も同じようにある一定のラインをこえるとスイッチが入るのでしょう。
数日のズレは起きてしまう可能性が高いのですが、自分でも独自に予想ができるため、花見の日を決めやすいメリットがあります。
桜開花予測 400℃の計算方法
1日の平均気温の合計400℃に達したら開花
- 2月1日を開始日として計算
- 1日の平均気温を毎日足す
- 3月になったら天気予報を確認する(天気に左右されるため)
- 400℃が近づけば毎日桜の木に注視する
- 桜を見て、5~6花が咲いていたら、開花宣言(独自)
桜開花予測 600℃の計算方法
1日の平均気温の合計600℃に達したら開花
- 2月1日を開始日として計算
- 1日の最高気温を毎日足す
- 3月になったら天気予報を確認
- 600℃が近づけば毎日桜の木を注視する
- 桜を見て、5~6花が咲いていたら開花宣言(独自)
まとめ 桜の開花予想は自分でできる
ソメイヨシノは日本を代表する美しい桜です。
開花したあとは約7日で満開になります。そして、1週間ほどをかけて散っていく…。
楽しめるのは非常に短い期間。その間に大雨が降ると最悪です…。注意してみておく必要があります。
「400℃」と「600℃」。
「平均気温」と「最高気温」で足していきます。600℃のほうが簡単に計算できそうですね。


