十五夜は知っているけど、「十六夜?」と思っている人も多いのではないでしょうか?
この日にはどんな意味があるのでしょうか?
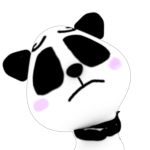
「じゅうろくや」?十五夜…、「じゅうろくや」ってなにパラ?
十六夜の読み方と意味

「じゅうろくや?十六夜!」
読み方は「いざよい」と読みます。
十六夜は、「じゅうろくや」でも正しいのですが、「いざよい」と読まれることのほうが多いです。
「いざよい」は、躊躇う(ためらう)という意味の動詞「いざよう」から名詞になったもので、月が出る時間は毎日50分ほど遅くなると言われています。
「どのような意味があるの?」
十六夜は、新月から数えて16日目(陰暦8月16日)の夜を指しています。十五夜の月よりも遅く、なんだか恥ずかしそうにためらっているように見えることから十六夜の月と呼ばれています。
十五夜と十六夜の違い

お月見をする十五夜は全国的に有名です。
十五夜は15日の夜だけではありません。十五夜は月が最も満月に近くなる日です。
旧暦の8月15日以外の月の15日も十五夜と呼びます。
要するに、十五夜は一ヶ月の中で、形が最も真円に近付く夜の月を指しています。一方の十六夜は十五夜を過ぎていることから真円から少し欠けた状態になります。
江戸の風習

十五夜、十六夜以外にも、十九夜、二十三夜、二十六夜などの特定の月齢の月があります。
この月を出るのを待ちながら、みんなで食事をするお月見の風習が江戸時代にありました。これを月待ち講(つきまちこう)と呼びますが、一度は聞いたことがあるかも知れません。
「講」は同じ信仰などを持つ寄合の意味を指し、月に神仏を結び付けて拝むことを「月待ち講」と呼びます。
まとめ 十六夜は月がほんの少しだけかける
毎日、月の形に気をつけていた江戸時代の人はすごいですね。
雨が降った日はガッカリしていたかもしれません。
月はロマンティックの塊です。




